先日、息子の発表会がありました。
私は園の役で、発表会の裏方のお手伝いをしてきました。
その時に、幼稚園の先生のすごいなって感じたんですね。
小規模幼稚園だから出来る事?
それとも、幼稚園の取り組みがすごい?
とにかく、子ども達をすごく大切に思ってくれているなっていうのが伝わってきたんですね。
息子が転園してから、すっごい成長したのは幼稚園の環境によるものも大きいなと改めて思いました。
今回、幼稚園の先生方ってすごいんだぜ!なお話をしていきます。
[s_ad]
大規模幼稚園と小規模幼稚園の違い
発表会も、大規模幼稚園の時と全く違っていました。
前方にカメラ席があって譲り合って座ったり、後方にパイプ椅子の席があるなどの席の配置は同じ。
しかし、園によって違うなと感じる部分は多かったです。
例えば写真撮影。
今の小規模園の方はカメラ撮影に対してかなり厳しいです。今回も撮影はOKだけど、SNSなどネットにアップすることは禁止しています。
撮影禁止の理由はこちらから
他にも、違うなと感じたことを挙げていきます。
舞台プログラム
大規模幼稚園では、1日ですべての園児の発表をすることが出来なかったので分割でした。
3日に分けて開催されます。
(〇組さんは1日目、△組さんは2日目のような感じ)
なので、兄弟がいる家庭は、バラバラの日程になると2日間行く必要があります。
上の子と下の子が同じ日程だと1日で終わるのですが、日程が違う場合は、上の子を連れて下の子の発表を見に行くという感じですね。
前に通っていた大規模園は、「こども園」ということもあり、2歳児さんの発表もあります。
2歳児さんはお遊戯だけして降園(もしくはその後預かり)というスタイルでした。
年少は、お遊戯と合唱・合奏
年中は、劇と合唱・合奏
年長も、劇と合唱合奏
それに、先生方の演奏もありました。
今の小規模園では、先生方が演奏したりという事はありません。
その代わりに、未就園児の発表がありました。(簡単な手遊び)
発表後はお土産をもらって帰るという、運動会の未就園児競技のような感じでした。
年少は、お遊戯と合唱
年中は、オペレッタと合唱・合奏
年長は、劇と合唱・合奏
それに加え、最初に園歌と最後に全園児での合唱がありました。
どちらの園も午前中で終わり。
終了後は、子どもとともに降園しました。
舞台演出
大規模園では、先生方と役員(上の役の方だけ)で準備や後片付けをしていました。
が!今の小規模園では、上の役員だけでなく、発表会の役になった保護者やボランティアの方(教育実習に来てた学生さん)もお手伝いをします。
さらに、最後の片づけは保護者全員です。
子どもたちの待機場所も違います。
大規模園では、待機している姿を保護者には完全に見えないようにしています。
発表の時だけ出てきて、終わるとすぐに廊下へ撤収という感じでした。
対して、小規模園では、出番の1つ前くらいから待機している姿が保護者席からガッツリ見えます。
入場の前に、子どもたちが親に手を振って「今から頑張ってくるよー♪」と舞台袖へ移動していきます。
この違いに、発表会での親と子の距離感が違うなぁって感じました。
簡単に言うと、大規模園は「園にお任せくださいスタイル」、小規模園は「保護者の方も協力してくださいスタイル」
子どものタイプによって違ってくるとは思いますが、我が家の場合は小規模園スタイルの方が合っていました←
子どもたちの衣装
大きく違ったのが子どもたちの衣装です。
大規模園では、指定の肌着を持って行き、園で用意された衣装に着替えるといった感じでした。
頭にかぶる帽子だけは、子どもたちの好みの色を取り入れたり、顔を描いたり、パーツを貼り付けたりしていました。
衣装は、後日綺麗にして園に返却。帽子だけ持ちかえりでした。
園で用意された衣装は、結構しっかりとしたものです。
見た目も可愛いです♪
それに対して小規模園では、完全に子どもたち監修。
色付きだったり、可愛い模様の入った大きなビニール袋に、首と手を通すところだけ開けたものを先生が準備し、後は子どもたちが好きに彩るというものでした。
お着替えのお手伝いをしたからこそわかったんですが、子どもたちは自分の作った衣装をすっごい大事にしてるんですね。
「ここにキラキラをくっつけて可愛くした。」「ここにハートを作ってくっつけた。」「格好よく見えるようにこの色を選んだ」などなど、子どもたちのこだわりポイントを教えてくれます(笑)
ビニール製のいかにも手作り品なので、既製品のような見栄えがいいものではないかもしれませんが、子どもたちの気持ちがめっちゃ詰まった衣装だなと感じました。
もちろん、息子も自分で作った衣装が大好きで、格好いいポイントをめっちゃ教えてくれましたよ♪
嫌がる子どもへの対応
もう1点大きく違いを感じたのは、嫌がる子供への対応ですね。
大規模園では、お遊戯の途中で座り込んでしまった子を、何度も先生が抱っこをして立たせるという場面があったり、上手く演奏できない子に厳しい対応をされていました。
当日エアーピアニカにされた子もいました。
今では、この状況は異常だったと思えます。。。
とにかく、皆のレベルに達せられない子に対しては辛いものがありました。
(当時は、皆と同じことが出来なくて罪悪感を感じることもあった)
それに対し、今の小規模園はかなり寛大だなと感じます。
舞台に立つのを嫌がる子がいて、舞台袖へ引っ込んでしまったとしても、舞台に立つことを強制しません。
息子のように、最後に力尽きて寝そべってしまっても無理やり立たせようとはしないです。
完璧でなくてもいい、子どもなりに楽しめればいいを重視してくれています。
発達に遅れがある我が家には大変ありがたい対応でした。
先生方の支えがすごい
発表会で息子が頑張れたのは、先生の支えによるものも大きいなと感じました。
裏方の手伝いをしなければ、気づかなかった事も多いです。
普段、子どもたちのことを考えてこんなにもしてくれていることに感謝しかありませんでした。
教室の黒板に先生手書きのメッセージ
教室に入るなり飛び込んできたのは、先生の手書きメッセージでした。
子どもたちの演奏する楽器、オペレッタの役のイラストが描かれており、「今日は本番!〇組さんがんばるぞ!」という、気合の入ったメッセージが付けられています(笑)
そのイラストを見て、子どもたちが僕の役はこれ!私はこの楽器!とホクホクしていました。
そういわれれば、運動会の時もそうだったのですが、お迎えに行ったときにも「あと〇日で運動会」と書いていたんですね。
今回の発表会も同様に「あと〇日で発表会」と書いており、お帰りの時に先生が子どもたちに「あと〇日だね~」からのポジティブな声掛けをされていました。
先生からのパワー注入
一番すごいなと思ったのが、この先生からのパワー注入です。
オペレッタのための着替えが終わった後に、先生による子どもたちにパワー注入が行われました。
「よし!皆がもっと頑張れるように、先生から皆にパワーをわけよう!」と、子ども達1人1人を抱きしめ声掛けをしていきます。
名前を呼ばれた子が先生に駆け寄ると、先生からのハグ。
そして、1人1人に言葉が送られるんです。
「めっちゃ練習してきたもん!〇〇くんが格好いい踊り出来るって先生知ってる。格好いいところお父さんお母さんに見てもらおう。」
「〇〇ちゃんのお歌、すっごい元気が出るお歌だから先生大好きだよ。本番でも元気なお歌聞かせてね。」
などなど、その子その子にドンピシャな声掛けをしていきます。
子どもの良いところをすっごい見てくれているからこそだなと感じました。
緊張のあまり泣き出す子もいたのですが、先生が優しく抱きしめて言葉を送ると、気持ちが切り替わったのか再び笑顔に。
幼稚園の先生ってすごいなと思った瞬間でした。
緊張を解す手遊び
移動直前に、緊張を解す手遊びをしていました。
「グーチョキパーで何作ろう~」ってやつなんですけど、子どもたちの楽器や役を作っていくんです。
普段もやられているんでしょうね。子どもたちは「次はカスタネットや―。」と喜んで手遊びをしていました。
締めるときはしっかり締める
子どもたちの気持ちを盛り上げるだけでなく、引き締めるところはしっかりと引き締めていました。
ぐにゃぐにゃになった息子への対応でも思ったことですが、本当にありがたい事です。
移動前は、「ホールに入ったら静かにしよう。皆、忍法静かの術でござるよ。」と声掛け。
静かに待てたら格好いいよねって話をしたり、ワイワイガヤガヤなっちゃったら先生が鬼に変身しちゃうかもーなんて話をしたり。
そして、静かに待てたら本気で褒めてくださいます。
「〇〇ちゃんの三角座りめっちゃ綺麗!」「〇〇くんすごい!めっちゃピシって並べてる!!」などなど、いろんな「出来た」を拾ってくれるのが素敵です。
出来ていることを認めてやる気を促し、危ない事はガッツリ叱ってくれます。
息子のように甘えモードになっても、軌道に乗ったらスッと引いて息子自身にやらせてくれたり、距離の取り方がさすがだなと思いました。
他のクラスの様子
息子の担任の先生だけすごいってわけではなく、他のクラスの先生もそれぞれ工夫されているなと感じます。
年長さんは男性の先生なんですが、毎回始まる前に気合を入れている姿をよく見かけます。
「〇〇組さん!今日は頑張るぞー!(オー!)」という掛け声をよく聞きます。
ライブ前の円陣みたいな感じですかね?とにかく、毎度先生と園児のテンションがすごいです(笑)
どの先生も、子どもたちの気持ちをあげ、頑張れるように促してくれるんですよね。
そういわれれば、息子の年少の時の担任の先生もよく「昨日は〇〇の踊り上手に踊れたんだよね。今日も先生見たいなぁ♪」と引き渡しの時によくいっていたことを思い出しました。
幼稚園の先生って本当にすごいです。
発表会を振り返り思う事
園によって、発表会のスタイルはかなり違います。
息子には、前の大規模園より今の小規模園のやり方があっていると感じました。
たぶん、問題を抱えていない子であれば、大規模幼稚園のスタイルでも大丈夫でしょう。
息子が今回やる気になってくれたのは、いろんな要素が重なってのことなんですね。
・先生方が息子のペースを大事にしてくれた
・自分のやりたい楽器や役を選ぶことが出来た
・自分で衣装を作ることで、作り上げていく感を味わえた
・「出来た」を感じ、私や主人に格好いいところを見せたいという気持ちになった
これらは園の環境や先生のフォローがあったからこそだと思います。
また別に書きたい事でもあるんですが、親だけで支えようとしてもだめなんですよね。
逆に先生だけで支えようとしてもだめなんです。
園と親、両方が一緒に支え、息子が前を向けたからこそ乗り切れたんだと思うんです。
幼稚園の先生方には、本当に感謝しても感謝しきれないくらいです。
息子が発表会を楽しめるようにフォローしてくださり、本当にありがとうございました。
来年、年長になってレベルも上がるんだろうけど、その時もまた協力しがんばっていけたらと思います。
参加中






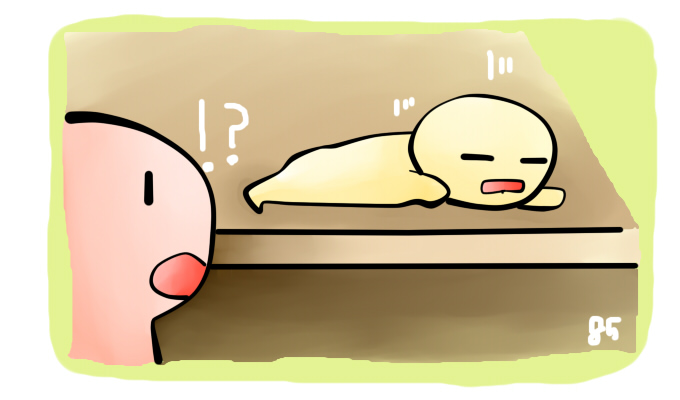
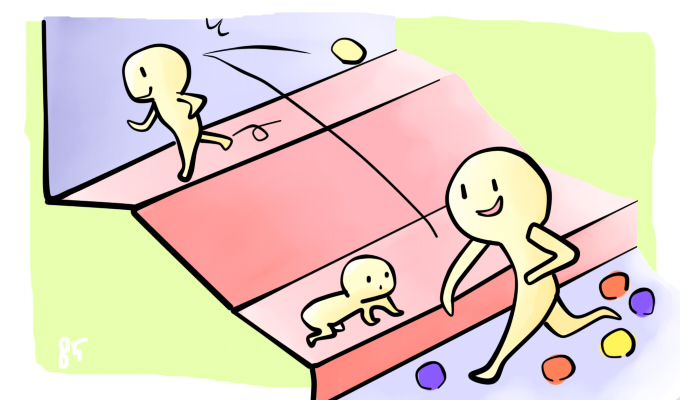
コメント
お遊戯の衣装ってよく先生が自分で材料用意して時間外に作って先生の物として年々貯めていくみたいに聞いたことあるけど、自分で作る事も大事だね。
子供が、自分の服の魅力を語ってくれるのめちゃ分かる😊可愛いし、みんながいっぱい教えてくれるよね。
ウルちゃんの園の「完璧じゃなくても大丈夫」スタイルだからこそ、そのキリキリしてないやり方が子供にとっては出来るように心の準備が出来たら頑張りたいと言う気持ちを生み出すんだね。
これ、大人になってもとても大事な事だよね。私正社員だと頑張りすぎて引かれるんだけど多分この「出来ない事がある時があっても大丈夫、出来る時もやってくる」と言う構えが出来ないからな気がする。
息子にはぜひ柔軟な気持ちの対応が出来る子になって欲しいな。これはきっと子供の頃の経験が大人になって響くよね。
ノンさん>コメントありがとうございます!
発表会の衣装も園によって違うんだなぁって感じました。
園によっては、ノンさんが仰るように先生が準備するところもあれば、基本の形を指定して、後は親が頑張って作るっていうのもありますし。
それぞれ良いところがありますよね♪
子どもたちの手作り衣装は、既製品に比べると見た目華やかではありませんが、子どもたちの気持ちがいっぱい詰まった素敵な衣装でしたよ(*´▽`*)
今朝、園長先生と少しお話したのですが、園長先生が「息子君、しんどいところもあったかもしれんのによく頑張ってくれた!」って言ってくれたんです。
「息子君、楽しそうにしていたから良かった」って。
前の園では、担任の先生はあたたかい言葉をくれたけれど、副園長先生は「息子君だけ~」だったり「年少だからいいけれど、年中では~」ばかりだったんで、今の園の園長さんの「息子君が楽しいと思えたことが一番」って言葉は本当にありがたかったです。
ほんと、いろんな「出来る」を拾ってくださるからこそ、自身がついてやる気に繋がっているんだと思います。
そして、ノンさんの大人になっても大事な事っていうのに共感です。
私が勤めてたところの大半は、新人に対してすっごい冷たかったり不親切だったりしました。
今だから思うけど、経験値のあるベテランと新しく入ってきた人だと仕事に差が出てもおかしくないんですよね。
なのに「これだから新人は~」みたいなのがあって、しかも「新人の頃は皆その道を通ってきたから」で済まされるという無茶苦茶な状態。
これで頑張ろうって思えるのは、相当な打たれ強さがある方かと。。。
これね、経験値のあるベテランが大人、新人が子どもで考えるとすっごいわかりやすい(笑)
はじめから完璧を求められると、自分の出来ないが目についちゃってしんどくなっちゃうけれど、不慣れながらも出来たところを出来たねって認めてくれると、次も頑張ろうって思えますもん。
出来るまでに到達するのに、やらなくちゃいけないから取り組むのか、前向きに頑張ろうって思って取り組むのかでは気持ちって全然違ってきますよね。
自己肯定感をあげるには、きっとこういう積み重ねが必要なんだろうな♪