前回、K式の発達検査を受けてきたというお話をしました。
今回のお話は、発達検査の結果から、小学校生活を送る上で何を大切にしていけばいいかを考えていくお話です。
[s_ad]
息子の特性
息子は自閉症スペクトラムと診断されています。
こだわりがあり、マイペース度がかなり強く、集団行動が苦手です。
年長の今も、個別行動が多く、皆と一緒に行動できないことがあります。
年中の時と違い、ワンテンポ遅れて皆と同じことに取り組めるようになったりと進歩はあるものの、クラスメイトの中では浮いた存在です。
また、感覚過敏もあり、音や光、触覚が過敏です。
そのため、不安感や不快感からパニックになる事もあります。
今現在、息子自身も不安の回避の仕方を覚えてきたということもあり、パニックの頻度は減ってきています。
(ただし、地震や停電などの予告なしにくるタイプのものは苦手)
マイペースすぎて集団生活の馴染めなかったり、感覚過敏のことを考えると、普通級で過ごすのは厳しいと考え、支援級にお世話になる予定で就学指導を始めました。
発達検査の記事はこちら
発達検査の結果から、保健センターの相談員さんに言われた事
今のところ、私たち「保護者」「医療機関」「保健センター」は満場一致で支援級の情緒クラスという意見です。
そのため、就学指導自体は今のところスムーズに進んでいます。
あとは、面談で教育委員会さんに息子の困り感を伝え、なるべく加配をつけてもらえるように頑張るのみです。
今回、発達検査を受けた後に、保健センターの相談員さんから4つのことを言われました。
「認識のズレ」について
今はどちらかというと、入学後の不安がとても大きいです。
その理由が、保健センターさんから言われた「認識のズレ」からトラブルを起こしやすいであろうという事。
以前にも、「息子君には、社会が少し違って見えているんだと思う」って事は言われていました。
今回は「98%の人がこういうことだろうなって理解できるところが息子君には難しい。少しかすった違うところを受け取ってしまう。」と言われました。
なかなか衝撃的な言葉ではあるんですが、「あー。なんかわかるかも。」とも思ってしまいました←
例えば、年少の頃の話ですが、普通だったら落としたものを拾ってくれたら「拾ってくれてありがとう」ってなるんですけど、息子の場合「僕のものを取らないで!」ってなっていました。
「息子君のものが落ちていたから、お友達が拾って息子君に届けてくれたんだよ。」と言ってもなかなか理解できないのです。
何度か同じパターンを経験して、段々と納得して、〇〇な時は〇〇なんだなとやっと理解できるって感じなんですね。。。
私は息子の母親であるので、フォローし「こういうことだよ」って伝え続けていこうって思えます。
しかしですね、赤の他人だとよっぽどの人じゃないと、変なやつ。。。と距離を取って行くのではないかと。
幼稚園の今は、「みんなお友達!」みたいな感じで、みんな親切にしてくれているけれど、そういうのって長くても小学校の低学年までじゃないかなぁと思うんですね。
3,4年生ぐらいになるとしっかりグループが出来ていた記憶がありますから。
前に、自閉症協会の方が「成長するとともに対等じゃなくなっていく。それもそれで辛かった。」と言われていました。
先のことで、まだどうなるかはわからないけれど、息子も集団生活に馴染めず辛い思いをするんじゃないかなぁって不安はずっとあります。
「認識のズレ」について、どうしていけばいいのか悩みます。
小学校生活はとにかく「楽しく通えるかどうか」がポイント!
「認識のズレ」から孤立してしまい、「学校に行きたくない!」とならないかという不安が付きまといます。
医療機関や交流会でも聞いていましたが、やっぱり一番大切なのは「学校に楽しく通えるか」なんですね。
保健センターの相談員さんにも「出来る限り社会とのつながりを断たないようにしていけたらと思う。」と言われました。
実は、先月の話ですが、小学校のスクールカウンセラーさんも同じようなことを言われました。
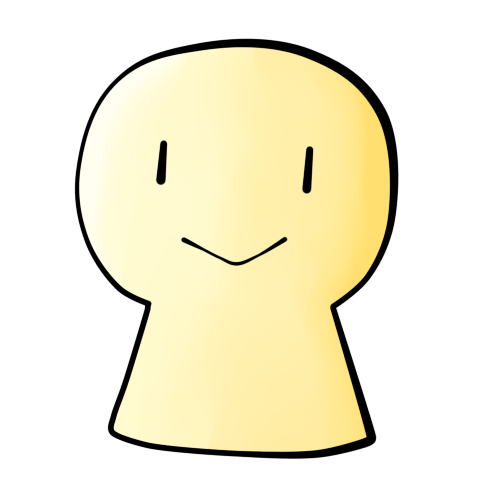
生きていくためには、人との関り方が大事かな
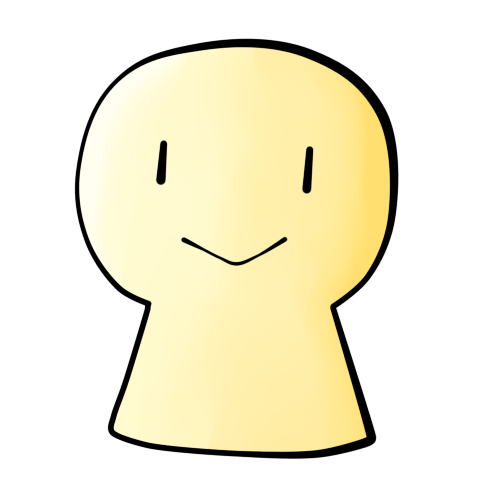
勉強がそんなに出来なくても、人と上手く関わっていけると生きやすくなるように思う
学校は勉強をするところですが、人との関り方を学ぶところでもあります。
なんだかんだ学習面の遅れが気になっていた私ですが、カウンセラーさんや相談員さんの言葉で、学習面もだけど社会に出るために人との関り方を学ぶ大切さを改めて知ることが出来ました。
だからこそ、支援級でサポートしてもらいながら、学校生活をなんとか送ることができたらという気持ちです。
就学予定の小学校の普通級の環境は、1クラスの人数や体制的にも、今の息子の段階ではしんどそうです。
「普通級」という所属にこだわるより、成長の段階に合わせて、どちらの方が子どもにとって学べる環境なのかを見定めていきたいです。
「安心できる場所で学ぶ」が第一ですね。
自己理解について
「自己理解」についての話も出ました。
自己理解と聞くと、就活などでよく聞きますね。
自分がどんな人間であるかを分析するみたいな。。。
自己理解ですが、息子の場合は「中学生になるまでは自己理解をすることは難しいと思う」って言われました。
いくら私が言ったところで、息子が理解できるもんではないと。
息子が自己理解をしていくのは、中学生になってからみたいですね。
そういった意味でも、小学校では何かあったときのフォローは必要だと言われました。
息子の特性的にも、お友達同士のトラブルも起こしやすいと思うので、頑張ってフォローしていきたいと思います(ヽ”ω`)
長い目で見てやっていきたい事
相談員さんに言われた最後のことは、「今は小学校の事で頭がいっぱいかもだけれど、就労までを考えなくちゃいけないからね。」でした。
確かに、今は小学校のことで頭がいっぱいです。
学校に通うことが出来るのかなぁ?と。
でも、当たり前ですが、小学校だけじゃなくて、社会に出るまでのことを考えていかなくちゃいけないんですよね。
就職できるかどうかっていう。。。もう果てしなく不安な部分です。
そこで、今からでもしていけることというのが「お手伝い」
「人の役に立てて嬉しいという気持ちを持てるから」だそうです。
仕事が好き!と思えるのならいいけれど、大半の人は喜んで仕事をやります!というよりか、お金のために頑張る!くらいの勢いです。
息子タイプの特性を持っている子は、離職する人もけっこういるそうで。。。
だからこそ、「人の役に立てて嬉しい!」という気持ちを持てるように、お手伝いをしてもらい感謝を伝える(手伝ってくれて助かったを伝える)をしていくのが効果的だと教えてもらいました。
お手伝いをしてた子は、離職しにくいそうです。
息子がしてくれたお手伝いに、もっと感謝を伝えていかなくちゃです。
この辺、トリプルPやIメッセージの伝え方が息子には効果がありそうですね!
発達検査から、今後のことを考えて
相談員さんから、いろいろな話を聞けたので、小学校で何を目標にしていけばいいのか見えてきました。
なので、前から気になっていたSST(ソーシャル スキル トレーニング)に力を入れいてる児童デイの見学に行ってきました。
社会性が低いので、今の息子に一番必要かなぁと。
(児童発達支援にも空きがあったので、契約してきた)
いざ通ってみないとわからないことだらけなんですけれど、まずは学校に楽しく通うための環境づくりをしていきたいと思います。
家、学校、医療機関と連携をとって、家では家で出来る事を精一杯やっていくつもりです。
社会とのつながりをなるべく断たないように、なんとか頑張っていきたいです。
参加中

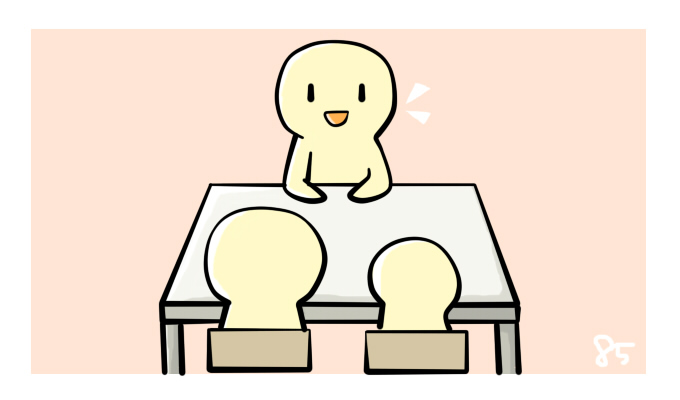



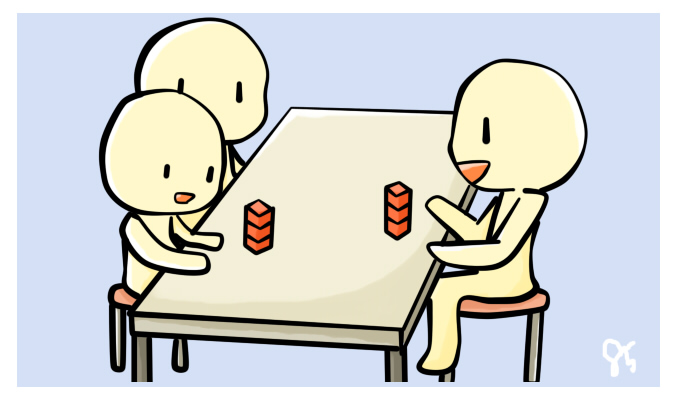
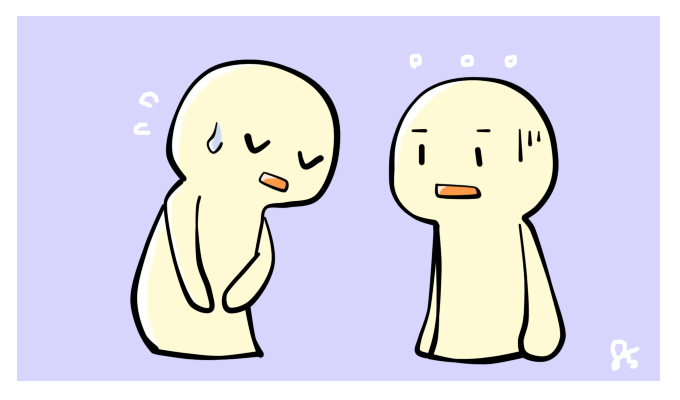
コメント